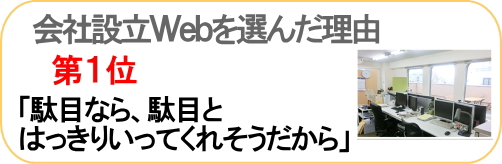
個人事業の方が有利なのに、会社設立してしまった事例
まず、言わなければいけません。
はっきり言って、多くの起業の場合、会社設立するより個人事業で起業した方が有利です。
でも、起業する人の多くが、個人事業だと恥ずかしい、会社設立しないと体面が取れないと思い込んでいます。
また、会社設立した方が個人事業より創業融資を受け易いという、都市伝説に捉われている人が多いのも事実です。
まあ、確かに、人材派遣業等は、そういう場合があるのは事実ですが、多くの業種は違います。
また、確かに、2012年頃までは、そのような傾向にあったのも否定はしません。
しかし、2016年現在は違います!
正直言って、商売するのに、「恥」とか「体裁・体面」なぞ不要です。
会社にすると税金の申告も難しいし、社会保険事務所からも調査したい等の連絡がきます。
大変なんです。
だから、手間がかからず、簡単な手続きで商売できる個人事業の方が有利な場合が多いのです。
これはそういう事例です。
事例1:遺品整理業者のケース
この会社は、創業融資の相談で来ました。
資本金10万円で東京の安い行政書士に依頼して株式会社を作り、相談に来た時点で設立から3ヶ月経過していました。
3ヶ月経過時点で、売上高は20万円程度でした。
もはや、税理士の顧問料も支払えない状態です。
こりゃひどい。
設立前の職業を聞いたら、一般的なサラリーマンで、勤務していた会社も全然違う職種(コンピューター関連)でした。
何故、遺品整理業で独立したのか聞きました。
2014年当時は、金の価格が高く、古物商の創業が流行していた関係で、遺品整理業を営むための講習が盛んに開かれていたので、講習を受けて起業したそうです。
何故、個人事業ではなく、会社設立したのか聞きました。
この業種は、会社設立する必要のない業種です。
どうやら、その会社設立業者に相談したら、会社設立を勧められたそうです。
何故、資本金10万円で設立したか聞きました。
貯金が30万円しかなかったので、資本金を10万円にしたそうです。
しかし、当然ですが、会社設立する費用に23万円かかったそうです。
次に、会社設立業者と利益計画の見通しを話し合ったか聞きました。
そのようなことをせずに、ただ機械的に設立代行したとのことでした。
<結論>
この事例は、会社設立業者の倫理観として、相手が絶対に会社設立したい!設立しないなら、他の業者を探す!といった強い要望の無い限り、会社設立を引き受けてはいけない事例です。
どうやら、会社設立した方が、創業融資が受けやすいと説明を受けたそうですが、
これは、まったくの嘘です。
政策金融公庫的な思考をすれば、資本金10万円で、未経験業種で、しかも、単に遺品整理業の講習会を受けた程度で、創業融資を受けさせるわけにはいきません。
保証協会的な思考をしても、クレイジーとしか言いようがありません。
理由は単純で、設立した瞬間に債務超過に陥っています。。
どう考えたら、この場合に個人事業より創業融資を受け易くなるのか、理屈がさっぱりわかりません。
この場合は、個人事業の方が有利なことを説明し、個人事業の起業の仕方を教えるべきです。
結局、お話を聞いた後、きっぱり断らせていただきました。
会社を作るのは簡単ですが、潰すのは大変なんです。
会社は、単に作ればいいってわけじゃないだろ・・・(溜息)
事例2:せどり輸出業者のケース
融資の相談で来た会社でした。
というか、うちの事務所に持ち込まれる相談は、融資ばっかりなので、当然と言えば当然ですが・・・。
いわゆる「せどり」でヤフオク等で買った商品を海外のeBayやAmazonで輸出販売する会社でした。
2015年は、円安で、多くの輸出業者が同様に当事務所を訪れた年でした。
かくいう私も、2016年現在、eBayのUSAとグローバルのトップレートセラーなので、この業界に関して、よく知っています。
正直、びみょーな会社でした。
もし、この会社が、株式会社ではなく、個人事業だったらまったく問題のない実績でした。
何故、「びみょー」かというと、この会社は、株式会社にした意味がまったくないのです。
まず、この業態は、取引先とかが法人組織を要求していないので、よっぽど売上高が大きくない限り、個人事業でなんの問題もなく運営できますし、むしろ個人事業の方が海外送金等を頻繁に繰り返す都合上、金融機関で口座を開設し易いので有利なのです。
更に、慢性的に赤字でした。
でも、その赤字幅が、びみょーだったのです。
つまり、赤字の原因は、税理士の顧問料と社会保険料負担、法人市民税が主な原因でした。
この業種の特徴は、消費税がすべて還付されるという恐ろしいメリットがあるのですが、株式会社の還付申請なので、税理士としても報酬を一般の他業種の会社より高く設定していました。
それは、消費税が戻ってくるのですから、当然といえます。
次に、そこそこ安定的に売り上げがあることから、ちゃんと役員報酬が出ていたのですが、法律上の義務として社会保険に加入していました。
そのため、この会社の経営実績では、経営者が独身だということを考慮すると、ちょっと負担が重い社会保険料が発生していました。
それにより、月当たり、毎月5万円程度が、びみょーに赤字なのです。
個人の通帳を見ても、ぜいたくしないで暮らしているのが見て取れました。
独立する前の会社員時代の年収も、国民健康保険料が負担になるほどの年収ではありませんでした。
なぜ、個人事業で開業しなかったのか聞きました。
同じく東京の行政書士が、安定した売上高が期待できるなら会社を設立した方が社会的信用が上がるので、銀行からも借り入れし易いと言ったそうです。
<結論>
個人事業でやれば、税理士の報酬もずっと安いというか、このレベルなら、
自分で申告できるレベルです!プロに依頼する必要はありません。
社会保険料も、独身なら、国民健康保険と国民年金、そして将来が不安なら、
国民年金基金に加入すれば十分です。
結局、この融資の依頼を引き受けましたが、代表者の融資希望額は500万円でしたので、それが減額される可能性が高いことを事前に説明し、300万円成功しました。
しかし、個人事業であれば、慢性的な赤字に陥ることはなかったので、もっと豊かに余裕をもって暮らせるし、むしろ融資も希望額の500万円を達成できたと思います。
このケースは、会社設立業者が、せどり輸出業に関して知識が無かったのが原因です。
私なら、個人事業のメリットをしっかり説明して会社設立ではなく、個人事業を勧めたケースです。
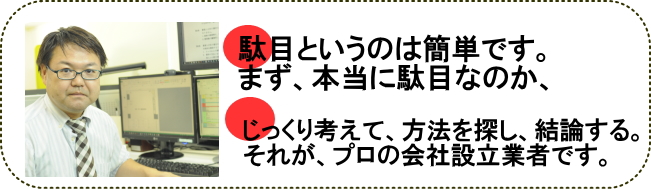
資本金の額の設定が間違っている事例
この事例には、さまざまなパターンがあり、枚挙にいとまがありません。
本来は、この資本金の額の設定こそ、会社設立業者に依頼する、本来の理由のひとつだと私は考えているのですが、この設定をいい加減に行う、安ければいいという会社設立業者が多過ぎるのです。
私は本当に怒っています。
ぷんすか。
この資本金の額というのは、基本的に大きければ大きいほど債権者の担保になるので推奨できるのですが、創業融資とセットで考えた場合、必ずしも大きければいいというものではないのです。
簡単に述べましょう。
「金(かね)、そんなにあんなら、融資受けなくてもいいですよね?」(にっこり)
まあ、当然です。
逆に、少ないのも問題なのは当たり前です。
起業するのですから、ある程度手持ちは貯めておかないと、創業前の努力が足りないと評価されるからです。
要は、ビジネスプランに応じて、適切な額を算出し、その適切な額に足りない場合は、どうしたら良いか考え、
適切な額を超える場合は、減らすのです。
このさじ加減こそが、会社設立業者に依頼する意味だと思います。
事例3:貯金600万円を全部引き出して資本金にしたケース
不動産業者のケースでした。
まず、健闘をたたえたいと思います。
素晴らしい!
よくぞ600万円も創業資金を貯めましたね!
でも、
この経営者の毎月の生活費は70万円でした。
資本金が多ければ多いほど、創業融資には有利だと会社設立業者から聞いて、有り金全部はたいて資本金にしたのです。
なんというか・・・。
困ったものです。
まあ、その会社設立業者さんは、横浜で最近よく知られている創業融資が得意と称する税理士事務所さんだそうですが、その事務所の紹介の銀行担当者が言った言葉は、
「資本金も多いし、不動産業だから、運転資金もたかが知れているので、創業融資希望額は、50万円でいいですよね?」
・・・こんなもんです。
代表者は、創業相談した時と全然話が違うといってびっくりし、公的資金相談Webに相談に来ました。
私は、その創業者に言いました。
高くつきましたね。
あなたは、これから選択肢のうち、2つを選ばなければなりません。
宅建業許可の申請を準備して許可が下りるまで、約3ヶ月
1)毎月の生活費70万円を会社から借金する。
2)代表者の役員報酬として、毎月70万円を会社に支払わせる。
借り入れた場合、約3か月間に増加する210万円を宅建業の営業許可が出て売り上げが立った時から、毎月の役員報酬から返済していくことになります。
また、役員報酬として毎月70万円を会社から支給させた場合、社会保険に加入しなければならないので、最初の売上が立ってもいないのに、その負担も生じます。
1)、2)どちらもそうですが、元は、自分の貯蓄なのに、気前よくすべて資本金にしてしまったことから、自分が会社から役員報酬という形で引き出すごとに、所得税を納めなければなりません。
つまり、あなたは、国に所得税を寄付したのです。
はっきり言うと、あなたの会社の適正資本金は300万円です。
私なら、300万円の資本金で会社を設立しました。
<その後>
その会社の創業融資のコンサルタント業務を引き受け、600万円成功しました。
まあ、余裕です。
資本金300万円でも同じ結果だと思います。
業者紹介の銀行提示額50万円がいきなり600万円です。
代表者は感謝していました。
でも、私は、
初めから、会社設立を当事務所が引き受けていれば、無駄がなかったのにと残念でした。
事例4:出資不能の現物出資のケース
古物商の事例です。
代表者の知り合いの司法書士が設立した会社でした。
創業融資を受けたいというので当事務所に来ました。
資本金は500万円でした。
内容を確認しました。
やっぱり現物出資が300万円紛れ込んでいました。
現物出資の内容は代表者のマイカーでした。
実際の現金出資は200万円でした。
まあ、現金200万円あって、同業種の勤務経験も7年近くあるし、
なんとかなるかなあ・・・。
山田「では、現物出資した車が会社名義になったことが分かる車検証のコピーを見せてください」
代表者「ありません」
山田「は?」
山田「車検証がないと、会社の経理で減価償却費の計上を今の税務署は認めませんよ」
代表者「マイカーローンの残債が残っているので、ディーラーに聞いたら、残債を払い終わるまで、所有権の譲渡はできないそうです」
山田「残債はいくらですか!?」
代表者「300万円です・・・」
山田「ふざけんな!!出資義務違反じゃないか!」
<結論>
司法書士は、登記のプロフェッショナルですが、会計分野の勉強をしている人が少なく、プロだと思うと、こういう事例がぱらぱら出てきます。
大学教育の弊害ですね。
逆に、税理士は、許認可や法律に弱い傾向があり、困らされます。
まあ、安くて、経験の少ない行政書士よりは、全然、マシ。
でも、このケースは本当にひどいですね。
この人のビジネスプランなら、資本金200万円で十分です・・・。
結論は、「論外」です。
当事務所で会社設立していれば、なんの問題もなかったと思います。
現物出資のときは、普通より注意して会社設立して欲しいものです。
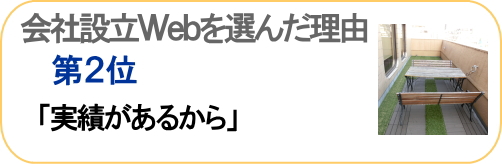
「法人成り」の際に、資本金の額の設定が間違っている事例
これは、個人事業で最初開業し、法人組織に変更する際に会社設立する事例です。
ここで重要なのは、「法人成り」というのは、法律用語でも会計用語でもなく、
「いわゆる」法人成りという、俗称だという点です。
また、この方法は、誰かから偶然教わるケースが多く、定まった形式がないのも特徴です。
そのため、多くの会社設立に携わる司法書士、行政書士、税理士、会計士といった会社設立業者の殆どが間違った手続きをしてしまっているのが実情です。
この手続きの間違いが致命傷となり、個人事業でうまくいっていた事業者が、会社に組織変更した時点から、銀行融資や許認可が受けられなくなるケースが、本当は多数存在しています。
私も、多数の事例を目撃しており、
本当に、迷惑をしています。
勿論、会社設立Webは、正しい「法人成り」の手続きを理論と経験から独自に構築しています。
胸を張っていいましょう!
「法人成り」なら任せてください!
法人成りする事業者は、基本的には2年以上の事業実績があり、個人事業が安定し始めたので、消費税等を考慮して会社設立する事業者が多いのですが、中には、個人事業で創業融資を受け、それをきっかけに会社設立して法人成りする事業者もいます。
事例5:他人から500万円を借り入れて資本金としたケース
建設業の事例です。はっきり言って続出事例と言っていいくらい、よくある失敗事例です。
失敗の原因は、この資本金500万円という数字の勘違いから始まっている場合が多いです。
何故、「法人成り」という言葉が、俗称で、法律用語でも会計用語でもないかにも関わっているのですが、
個人で建設業許可を取得していても、会社を設立すると、会社は法人という別人なので、許可を新規に取り直しになってしまうのです。
つまり、個人と会社は、法律的に別人なので、「人格を継承できない」から、法人成りというのは、法律用語でも会計用語でもないのです。
建設業の新規の許可を取得する際の要件に、資金調達力が500万円以上ある必要があります。
この500万円というのは、資本金である必要はありません。
請け負った工事の代金の回収に支障が出た場合、下請け先に資金繰り上の連鎖被害を出さないように、あくまで一時的な資金調達力を確認するための要件です。
それを勘違いして、資本金が500万でないと建設業の許可が取れないと誤解するケースが後を絶ちません。
また、プロであるはずの、会社設立業者も勘違いしていたりするから、困り果てるわけです。
さて、
この建設業者の場合は、個人事業における「純資産」(資産から負債を控除した額)が300万円であるにも関わらず、他人から一時的に借りた500万円を金銭出資し、
会社設立後、ごっそり500万円を返金してしまいました。
そして、
そのことが原因となり、使途不明金が500万円生じ、銀行等の金融機関が追加で資金を貸してくれなくなってしまったのです。
なぜ、このような会社設立をしたのか聞いたところ、
個人事業時代に顧問契約をしていた税理士が会社設立したそうです。
<結論>
他人から一時的に500万円借り入れて資本金を500万円にするのではなく、資本金を300万円とすれば、このような問題はまったく生じず、
肝心の建設業の許可も、その知人の力を一時的に借りれば、ちゃんと取得できたはずです。
こんな基礎的なことも分からないのに、会社設立業者を名乗られると迷惑です。
事例6:創業融資の金額すべてを資本金として法人成りしたケース
このケースも最近、政策金融公庫で創業融資を受けた経営者が陥りやすいケースで、頻出ケースです。
政策金融公庫は、創業前でも積極的に事業資金を貸し出してくれるとてもありがたい融資機関です。
保証協会付銀行融資では、まず考えられないですね。
さて、
今回の事例は、中古自動車販売業でした。
中古自動車販売業の創業者は、資本金をできるだけ多く見せたい見栄っ張りな人が経験上、とても多く、
よく500万円を一時的にどこからか借り入れて、資本金にし、
そのお金、どこから手に入れたか聞くと、不思議と皆、口を揃えて、自分の車を売却したと答えるのが面白いです。
だから、私も銀行も、保証協会も、「中古自動車の融資」と聞くと、「ひとすじ縄じゃいかないぞ!気を引き締めていくぞ!」
と、ピリピリしてしまうのが実情です。
今回もそういったケースでした。
つまり、創業前に自己資金200万円で、政策金融公庫で300万円を創業融資を受け資本金500万円で会社設立していました。
・・・
なんで、こんな会社設立するんだよ!!(怒)
この事例の場合、顧問を引き受けた税理士の知り合いの行政書士が設立したそうです。
また、このパターンか!いい加減にしてくれ!
今回の依頼は、創業融資の当初希望額が700万円だったのに、300万円しか融資を受けられなかったので、追加で銀行の保証協会付融資を400万円受けられないかという相談でした。
問題となるのは、個人で政策金融公庫から借り入れた300万円の流れです。
この場合の会社設立は、融資的思考では、「法人成り」として扱うのです。
従って、法人成りの手続きがどのように行われたかを確認する必要があるのです。
そして、政策金融公庫からの300万円は、会社の債務として承継することが必要です。
すると、やはり300万円の使途不明金がでてしまうのです。
更に、法人成りをすると、保証協会によっては「創業融資制度が使えない」と判断される場合があるのです。
案の定、通帳の流れをみると、
政策金融公庫から創業融資300万円が振り込まれた日に、そのお金をそのまま代表者の個人名義の通帳にそっくり振込み、その300万円と自己資金200万円を使って同日に資本金500万円の証明をして会社を設立していました。
こりゃ、詰んでる。
言い逃れできんわ。悪いけど、パス。
その税理士と行政書士に責任取らせてくれ。
<結論>
断りました。
もっと考えて、会社設立してください。
本店所在地の設定が間違っている事例
本店所在地は意外と重要です。
基本的にはレンタルオフィスは避けてください。
理由は、融資を受ける際に、「実体がない」として断られる可能性が高いからです。
要は、そこに行けば、殆ど確実に経営者に会うことができる場所を本店所在地にするべきです。
次に、法律的に違法な状態にないことが必要です。
また、許認可の問題で、その本店所在地では許認可が取得できない場合があります。
しかも、業種によっては、県ごとに取り扱いが違う場合すらあります(例:古物商)。
そのため、許認可行政に強い行政書士が創業のコンサルタントには、適しているのです。
事例7:数県をまたぐ事業で、本店をレンタルオフィスにしたケース
見栄っ張りな創業者さんのケースです。
私は、商売に見栄とか外聞なんてないと思います。
でも、見栄とか外聞を気にする創業者さんて、多いんです。
今回のケースは、千葉県と埼玉県で他社の事務所の一部を間借りして営業していました。
ちなみにご自宅は神奈川県でした。
でも、本店は東京都のお洒落なレンタルオフィスでした。
登記もそのレンタルオフィスでした。
レンタルオフィスには、その会社さんの占有スペースは机ひとつです。
代表者さんの話では、「お客様と商談するのに、このレンタルオフィスの住所と設備がカッコいい」とのことでした。
代表者「当社は、最近業績を伸ばしているので、融資を受けたいです」
私「無理ですね。実体がない」
代表者「ここに実体があるじゃないですか!?」
私「机一つが実体だとおっしゃるので?
しかも、この契約はこのビルの所有者の同意が無い。
いつでも辞められて、継続性が感じられないレンタルオフィスを本店にするような外観上の信用が感じられない会社に、公的資金を借りさせろと?
はっきり言います。貴方が借りられるのは、日本政策金融公庫なら可能性がありますが、東京都信用保証協会では、見込みがないです。なにせ、実際の事業をやっている場所すら東京都ではなく千葉県と埼玉県。
しかも代表者の住所は神奈川県。
更に、千葉県と埼玉県の事務所も間借り(転貸借)で、ビルのオーナーの承諾がない、契約違反状態。
東京都だけではありません。千葉県でも埼玉県でも保証協会は融資を認めないでしょう」
代表者「では、利益が出ていても借りられないのですか!?」
私「はい。利益云々ではない。貴方は現在、融資難民だ。融資籍をどこかに手に入れない限り融資は受けられない」
営業目的が間違っている事例
これは、許認可行政に直接携わっていない会社設立業者に依頼すると、多々生じるケースです。
確かに、公証役場で、定款認証もできれば、法務局で登記できる。
だから、これが問題だと設立時点は気付かないのですが、
いざ、許可申請をしようとすると、「この目的では許可申請できないので、変更してください」と言われてしまうケースです。
代表的な例を挙げておきます。
事例8:介護事業者のケース
介護事業の創業融資の相談にいらっしゃった会社経営のお客様でした。
登記簿謄本の目的をみたら、
「介護事業」
と書いてありました。
目が点になりました。
私「代表者さん、これではそもそも介護事業の認可申請ができない。だから創業融資とかの前に、目的変更してください」
代表者「これは、信頼のある司法書士さんに依頼したので、間違いなくて、法務局でも登録されています!(怒)」
私「私の言うことが嘘だと思うなら、県の担当部署の電話番号を教えるので、その登記簿謄本を持って、相談に行ってください」
--後日--
代表者「言われた通りでした・・・」
定款の目的は、単に登記ができればいいというものではありません。
許認可の必要な業種の場合、行政庁から定款の目的の記載例が予め定められている者があります。
だから、定款の作成は、許認可行政に強い行政書士が、最もお勧めな理由です。
取締役の設定が間違っている事例
取締役の設定には、特に次のことに注意する必要があります。
1)金融等の信用情報に問題がない人物か
2)取得したい許可の取得に当たって必要な人物か
3)会社の経営に当たって有用な人物か?
主に上記の3点が必要です。
ここでは、代表的な事例である建設業を挙げておきます。
事例9:建設業の経営管理責任者がいないケース
建設業の許可を考えている会社の場合、取締役の中に、経営管理責任者が必要です。
この経営管理責任者になるには、建設業の内、同業種の個人事業の経験が5年以上(他の業種の建設業の場合は7年以上)、
建設業の内、同業種の会社の取締役の在任期間が5年以上(他の業種の建設業の場合は7年以上)、
客観的に証明できることが必要です。
この、「客観的」という語句がくせ者で、かなり難しいです。
この経営管理責任者がいないと、建設業の許可は取得できません!
従って、許認可を取得する予定のある会社の設立は、許認可行政に強い行政書士に依頼するのが適切なのです。
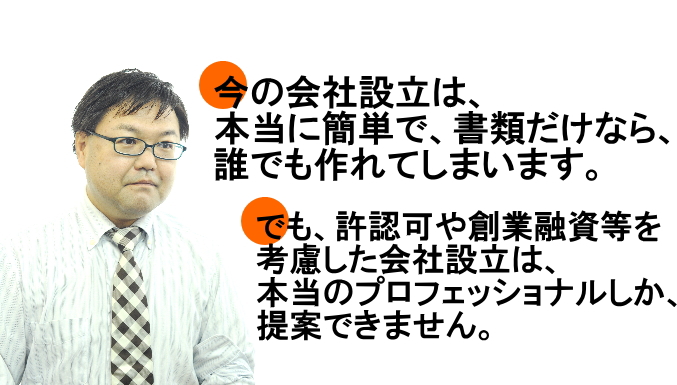

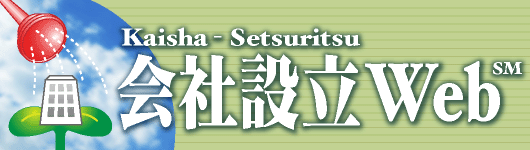
「へたくそ」な会社設立業者には、私も困っています。実例を紹介するので参考にしてください。プロの会社設立Webの手数料でさえ、たった15000円(税抜)なので、検討してみてください。
ログイン