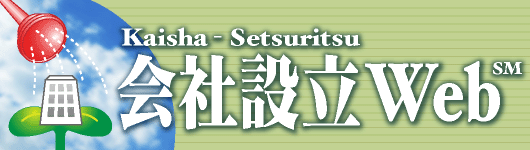会社設立した後の社会保険の加入は、強制加入です!
平成29年時点、これが現在の原則です。
しかし、平成19年頃は違いました。
当時も社会保険に関しては法人は強制加入でした。
ところが、設立したての会社が社会保険に加入しようとして当時の社会保険事務所を訪ねると、設立したての会社は強制加入だけど、実際には加入しなくて良いと社会保険事務所の職員に事実上、面談と称する話し合いで断られていたというのが実情です。
理由は、経営が安定していない会社が加入すると、保険料を滞納する場合が多く、その取り立てに膨大な手間がかかり、取り立てコストが肥大化し、事務を圧迫するので、経営が安定するまで加入しないで欲しいということをはっきり言われました。
これは、当時私が横浜市の鶴見社会保険事務所で職員に言われた言葉です。
現在は、このような指導は行われず、日本年金機構に再編され、逆に強制加入だから加入しなさいというスタンスに豹変しています。
従って、強制加入です。
但し、次の場合は加入しなくても構いません
それは、1)取締役しか存在しない(正社員等がいない)会社で、2)取締役の役員報酬が未だ捻出できない(0円)会社です。
理由は、保険料というのは、本来、(役員)報酬に一定の乗率を掛けて計算されます。従って役員報酬が0円なら、どんな乗率を掛け合わせても保険料は0円なので、保険に加入できないのです。
確かに、詳しい人は、標準報酬月額の第1等級を適用すれば保険料は徴収できるという考えもありますが、その標準報酬月額という制度は大正11年に社会保険事務の便宜上制定された制度なので、やはりその根本には、そもそも(役員)報酬が無い(0円)では保険料が発生しないという考え方があるのです。
従って、業績の悪くなってしまった会社においては、(役員)報酬が出なくなって(0円)しまうと、強制加入適用事業所を脱退することが実務上できるのです。
このことからも、(役員)報酬が0円の場合で、正社員等がいない場合は、社会保険に加入しなくてもよいことが理解できると思います。
でも、社会保険に加入しないと家族や自分自身が医療機関の診療を受けることができなくなってしまいます。
どうしたらよいのでしょうか?
そこで、会社設立したばかりの経営者には、社会保険に加入するか、任意継続するか、国民健康保険に加入するかのいずれかの選択をする必要が生じるのです。
保険証を手にするための選択肢はこの3つしかありません。
社会保険加入、任意継続、国民健康保険のどちらにするかの選択の指針
皆さんが一番気になるのは、やはり月額いくら負担すればいいのかということに尽きるでしょう。
やはり会社設立時においては、経営が安定するまでできるだけ切り詰めて暮らさないといけないと考える人が多いと思います。(まあそれは、経営が安定してからも死ぬまでずっとそうでしょうが・・・w)
そこで、毎月かかる金額に関する指針を述べることで選択の意思決定を容易にしたいと思います。
まず、ここで聞きなれない言葉かもしれないので、言葉の説明します。
「任意継続」とは
任意継続とは、会社員時代に加入していた社会保険を継続する方法で、会社を辞めた後、20日以内に全国健康保険協会(又は健康保険組合)に自ら申し出ることで、会社を辞めた日にさかのぼって社会保険に加入できる制度です。
一般の社会保険と違う点は、傷病手当金と出産手当金が支給されないということです。
そして、最長で2年間しか加入できないということです。
選択指針その1.「会社員時代の年収額が5,000,000以上か」
ざっくり言うと、平成29年時点において、年収5,000,000円の給与以上をもらっていた人は、任意継続した方が有利なことが多いです。
なぜかというと、それ以上の給与の人でも、任意継続加入した場合、保険料が月額280,000円(年収3,360,000円)の人と同じ金額で社会保険に加入できるからです。
すなわち、会社員時代の給与が280,000円を以上の人が任意加入した場合の社会保険と年金の負担総額は、神奈川県の場合(県ごとに社会保険料が少し違う)、平成29年9月時点は、
32,424円(40歳以上の場合)+国民年金16,490円(奥さんがいる場合2倍)
この金額は、前年度年収5,000,000円の場合の国民健康保険と国民年金の金額とほぼ同額です。
従って、年収5,000,000以下の人の場合は、社会保険に加入するか、国民健康保険に加入する方が有利なのです。
選択指針その2.「社会保険に加入した場合の最低保険料と比較する」
では、社会保険に最低の(役員)報酬額で加入した場合、月額保険料はいくらになるのでしょうか。
まず、最低限社会保険に入るための(役員)報酬額は、62,999円未満です。
この場合、平成29年9月時点の月額社会保険料額(神奈川県の場合)は、
6,717円(40歳以上の場合)+厚生年金16,104円(奥さんがいても変わらない)
つまり、月額22,821円!となります。
安いですね!特に奥さんがいる場合、奥さんの国民年金を払わなくて済むのが大きいメリットです!
デメリットは、(役員)報酬を62,999円未満と決定してしまうことになるので、その年の会社の会計期間において、急に業績が良くなっても、役員報酬を会計期間の途中で増やすことができず、法人税等が節税的な見地から見ると無駄になる可能性があります。
選択指針その3.「奥さんが社会保険に加入している場合、扶養になる」
(役員)報酬を0円にすることが条件ですが、
奥さんの扶養に入れば、新たに発生する保険料が0円になり、家計に新たな負担がまったく掛かりません。
国民年金も自分の分を納める必要がなくなります。
最高の方法といえるでしょう。
選択指針その4.「社会保険に加入する時期 年収1,300,000円が目安」
これまで、選択指針1から3迄述べてきましたが、
私が考える、社会保険に加入する時期というのは、奥様の扶養に入ることができない年収1,300,000円程度の(役員)報酬を安定的に支払えるようになる時期だと考えています。
それは、月役員報酬額が、108,334円ということです。
この時の月額保険料(神奈川県の場合)は、平成29年9月時点で
12,738円(40歳以上の場合)+厚生年金20,130円=32,868円になります。
これが支払えるようになったら、会社は経営の第一段階をクリアしたといえるでしょう。以後は、社会保険もそうですが、社会に貢献することを考えながら経営をしていくのが目標です。
最後に 社会保険に加入するのは無駄ではありません
今迄の内容では、ひょっとすると社会保険には加入するべきではないとの趣旨に取れるかも知れません。
誤解しないでください。
経営が安定したら、できるだけ早く自分達の将来のためにも加入した方が良いと思います。社会保険は、一見、大きな負担に見えますが、社会保険の掛け金は半額損金算入でき、しかも将来の保障を考えると割の悪い取引ではないのです。
巷で云われているように、「まったくの無駄」とは決して言えません。
考えてみてください。
自分で運用して失敗したり、働けなくなるほどの年齢を迎えた時に年金なしで生活する不安を。
皆と同じように皆と同じことをする。
それは、最低限の安心を得られる最も簡単な資産運用なのです。
例えば、会社に利益が出た場合、どのような節税対策が最も望ましいかと指摘されれば、私は迷わず答えるでしょう。
法人税より、所得税が有利である。従ってできるだけ給与(役員報酬)で節税するべきだと。
役員報酬(給与)も税率が上がったら、社会保険に加入するべきだと。
理由は、税金で取られたら何も戻ってきませんが、社会保険を掛けて取られた分は、年金という形で将来戻ってくるからだと。
つまり、同じお金を使うなら、少しでも戻ってくる可能性のある方に掛けるのが賢いのです。
だから、私は社会保険に加入しています。